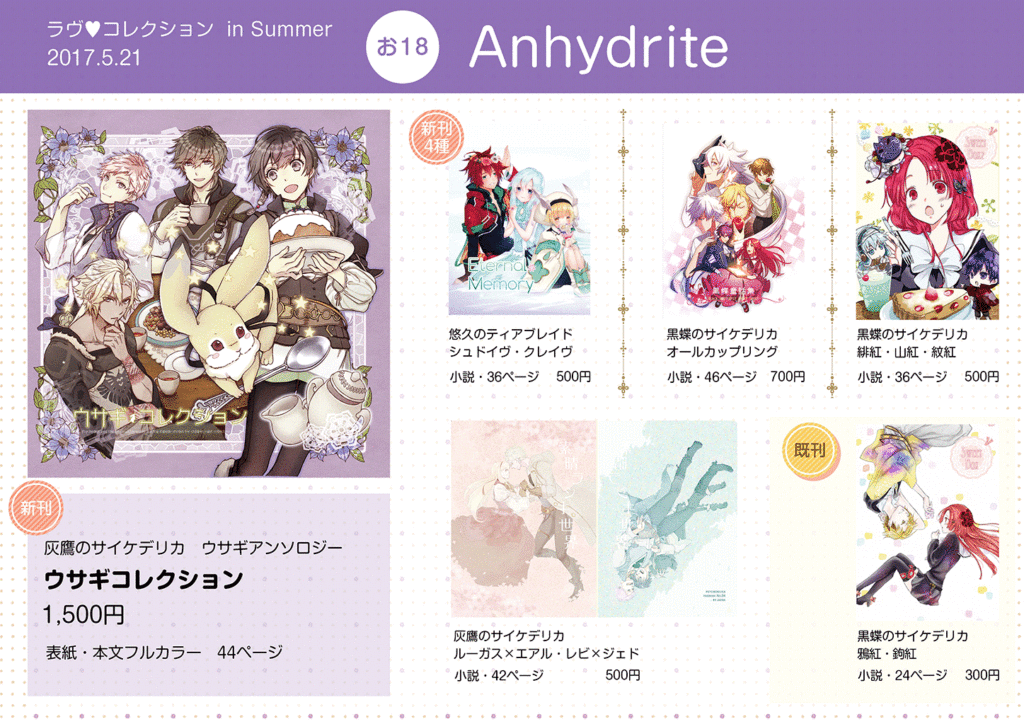私が想像する恋というものは、
例えるならこはるの髪の色のように優しい色をしていて、
例えるなら七海の髪の毛のようにふわふわとしたものだった。
でも、今の私にとって恋というものはそう――
「夏彦、そんなところで寝ていると風邪を引くわ」
部屋を覗くと、電池が切れたかのように机に突っ伏して眠る夏彦の姿があった。
追い込みらしく、寝る時間も惜しんでいたのは知っていたし、ようやくさっき片付いたというのも雪から聞いて知っているから寝かせてあげたかったが、どうせ寝るならベッドの方が良いだろう。
夏彦の体を揺すると、眉間に皺を寄せたまま夏彦は目を開いた。
「深琴か…」
「ええ、そうよ。ほら、ベッドに移動しましょう」
夏彦の腕を引っ張ると思いのほかあっさりと動いた。
と思いきやひょいっと私の体は宙に浮いた。
「きゃっ、ちょっ!」
「お前の方から誘ってくるなんて珍しいな。でも素直に甘えてくるのも悪くない」
「ちょっと!寝ぼけてるの!?」
いつもより饒舌にしゃべったかと思えば、ベッドに私を下ろしてのしかかってきた。慌てて夏彦の肩を押して抵抗すると、ようやく意識がはっきりしてきたのか焦点が私にあった。
「-っ!どうしてお前が俺の下にいる…?」
「あなたが運んできたのよ、今!」
「そうか…」
夏彦はため息混じりに深く息を吐いて、私の上に倒れこんできた。
さっきのように迫ってくるような気配ではなかったので、私も大人しく夏彦を抱きとめる。
「……夏彦?」
返事の代わりに届いたのは気持ち良さそうな寝息だった。
「お疲れ様、夏彦」
ぽんぽんと背中に触れ、私も目を閉じた。
どうせ夏彦を動かせないんだから、私も寝てしまおう。
そんな風に思えるくらい、私の気持ちは穏やかだった。
能力者として使命を背負っていた頃は、時間があるなら鍛錬をし、集中力を高めて、いつでも最大限の能力を発揮できるようにしていた。
そうやってずっと生きてきたから、能力者としての使命が肩の荷から降りた時少しだけ不安もあった。
夏彦がいるんだから何も心配することはない。
だけど、彼には彼のやるべきことがあって私には何もない。
彼を支えると決めた心は寝る間も惜しんで研究する夏彦の背中を見ているだけで時折折れてしまいそうだった。
だけど、少しずつ時間が経ち、能力者だった事が自分の中で過去になり、夏彦の隣にいる自分が現在に変わった。
目を覚ますと私の上に乗っていた夏彦がいなくなっていた。
慌てて飛び起きると、部屋の中はすっかり暗くなっていた。
夏彦の姿を求め、私はうろうろとしていたがふと窓の外を見ると綺麗な星空があった。
外に出て、あたりを探すと夏彦の姿を見つけた。
「夏彦」
「深琴、起きたのか」
「ええ。起こしてくれたらよかったのに」
「お前の寝顔を見てたら起こせなかった」
「…! 寝顔を見るのも駄目よ!」
慌てる私を見て、夏彦は目を細めた。
夏彦は、たまにそうやって私を見つめる。
それが少しくすぐったくて、私はいつも目を逸らしてしまう。
「綺麗な星空ね」
「ああ、そうだな」
顔を上げると、綺麗な星空に目を奪われる。
星って夏彦みたいだと思うようになったのはいつからだろう。
キラキラしていて、いつまでも目が離せない。
夏彦に恋をして、私は誰かを好きになる気持ちを知った。
それは決して想像していた優しい色でもやわらかなものでもなかったけれど。
でも、胸の奥で星のようにキラキラと輝き続ける―――不思議だけど、決して手離したくないものになった。
「ねえ夏彦」
「ん?」
「私、大分星座覚えたのよ」
「ほう。じゃあ、あれは?」
「あれはね―――」
夏彦が指差した星座を見て、私は得意げに口を開いた。
ねえ、夏彦。
あなたと過ごした日々は今までのどの時間よりもキラキラとしているの。
きっともう少し時間が経って振り返っても同じように輝いているのかしら。
それが分かるくらいずっと傍にいてね。